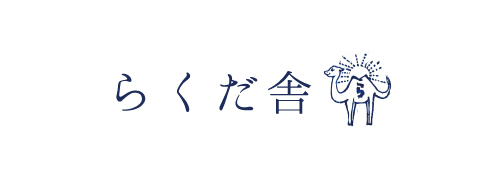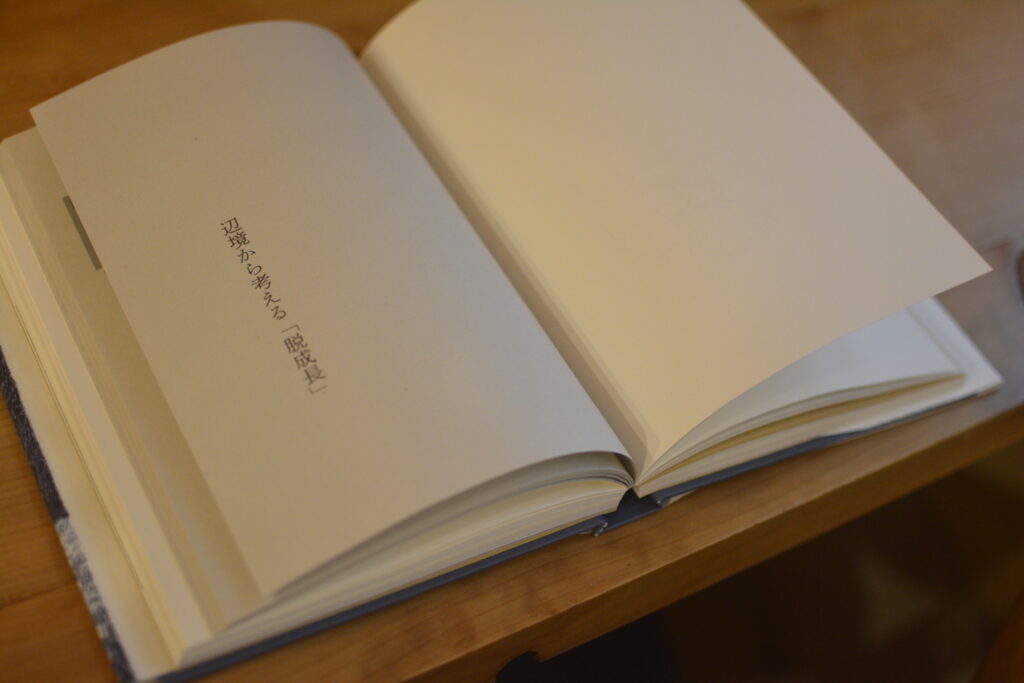11/26尾鷲市九鬼町で、穏やかな一日

『二弐に2』出版記念イベントとして、トンガ坂文庫さんと共催という形で企画させていただいた「らくだ舎と日曜日を漁村で」。
日中は、読書喫茶らくだ舎、と銘打って、九鬼町の喫茶スペース網干場(あばば)で喫茶店と本屋を出店しました。
コーヒーや、上ほうじ茶ラテなどの飲み物と一緒に用意したのは、二弐に2特別ランチプレート。
色川の野菜や卵、本著に取材文を掲載している山のハム工房ゴーバル(岐阜県恵那市)のソーセージ、ハム。
かつて色川に住んでいた友人で、二弐に2の印刷立ち会い時に再会したひかるちゃんがこねているルヴァン信州上田店の天然酵母のパン。そうした縁ある食べ物を集めました。

初めての場所で、準備が追いつかず、少しお待たせしてしまった反省もありつつ、
本を読んでから食べるゴーバルのハムソーセージは、ただ食べるのとは全く違った感じられ方をした、という声をいただき、
やってみてよかったなと思いました。
網干場はとても素敵な空間で、ふとした一瞬の風景が、心に残りました。
角Rの窓から見える水面のきらめきが店内に満ちて、本の上をゆらめく。
本を読んだり、仕事をしたり、思い思いに過ごす人たちの背中。
久しぶりの人と話したり、散歩に行って帰って来ておやつを食べたり・・・
訪れてくれた人たちの「居場所」になって、なんともいえない心地よい空間になっていたように思います。
また、九鬼町に暮らす方々も飛び入りで食べに来てくださって、美味しかったよ、と言ってくださいました。
これまで、トンガ坂文庫さんのある町、として九鬼町を眺めてきたのですが、
他の町の方々と接する機会になったことで、九鬼町という場所の輪郭が見えてきた気がして、その土地がもっと好きになりました。
色川から来てくれたT山さんやKちゃんのおかげで、たくさんお散歩して、旧九鬼小学校で遊んで、娘も大満足の一日になったようです。
とくに頼んできてもらったわけではなかったのですが、
いつもそうして支えてくれる人たちがいるおかげで、らくだ舎、千葉家はなんとかやっていけていることを、この日もまた感じました。
夕方〜夜にはトークイベント。制作の裏側を話しました

17時半からは、お店を閉めたトンガ坂文庫の本澤さん、豊田さんも合流して、網干場でトークイベントを行いました。
二弐に2購入者ともう一名まで無料、ない方は1000円で本を1000円割引、として設計しまして、
本制作の裏側をお話するような内容です。
本澤さん、豊田さんに質問いただいて、私たちらくだ舎の二人が答えていく形式。
どのように企画して、進めていったのか。寄稿者の方々は、どんな理由、どんな気持ちで依頼していったのか。
装丁とブックデザインを担当してくれた、fulbrn factoryのふたりも参加してくれたので、
その場で、デザインコンセプトをどうやって練り上げていったか・・・
200年残す、200年前の本、タイムレス、といったキーワードがあったことなども、話してもらうことができました。
印刷の苦労、製本や仕様でこだわった点なども。
質問にお答えする場面では、このような質問をいただきました。
「出版前と後で、どんな気持ちの変化があったのか」
「この本の出版は、一般的な本の出版とはまた違った意味を持たせようとしている意図を感じるけれど、そのあたり意図していることとしてはどんなことがあるか」
良い質問をいただいて感謝です。
その時しっかり答えられなかったような気もするので、さらに自分たちの中で考えて、
また改めてどこかの場面で、お答えできればいいなと思っています。
二弐に2の本を持たずに参加いただいた方も何名か来てくださったのですが、皆さん本を購入してくださって、ありがたい限りでした。
参加してくださった皆さん、トンガ坂文庫さん、ありがとうございました。
また今度は、読書会でお会いしましょう。
(らくだ舎 千葉貴子)